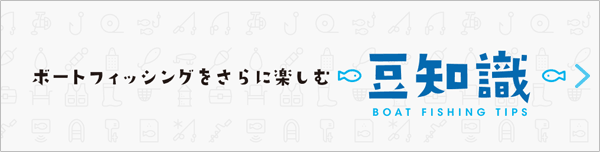【その15】先人の技、紙塩の方法
余分な水分を抜いて魚本来の味を引き立たせ、保存効果も上がる紙塩の手順をご紹介します。
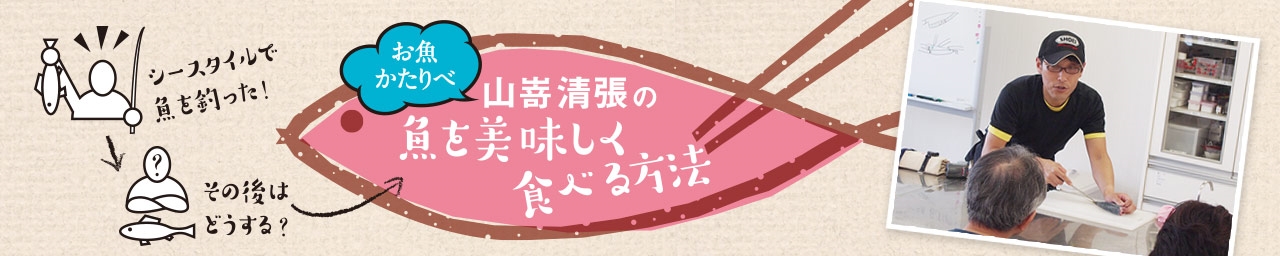
余分な水分を抜いて魚本来の味を引き立たせ、保存効果も上がる紙塩の手順をご紹介します。 会報誌See Sea Style vol.40 [2025.03] 掲載 <文・写真:お魚かたりべ 山嵜清張>
春の陽射しに誘われ、心は海へ。狙いの漁場に季節を届けるかの如く回遊魚が入り込み、根付きの魚たちも水温上昇に合わせて活発に動き出していると想像するだけで、期待が昂ぶります。
釣果は何日にも分けて楽しむこととなりますが、思い入れのある自分が釣り上げた魚は、美味しく、身質を落とさず、少しでも長く味わいたい。もちろん、魚は他のどんな食材よりも気を遣って保存しているつもりですが、時間経過、鮮度落ちで、大きく味が変化してしまうことは避けられません。
生食する刺身はもちろん加熱調理する場合も、少しでも良い状態を保ち、味わいたいという思いに、先人の技ともいえる和紙を使う技法、紙塩があります。
先人の技ともいえる和紙を使う技法、紙塩があります。
紙塩は塩の効能により、余計な水分を抜き、本来の味を引き立たせ、保存効果を上げ、色変化まで遅らせることを可能にします。とても簡単ですのでお試しください。調理バットかまな板の上にラップを敷き、そこへ塩を薄くふります。A4紙面相当に塩少々(親指とひとさし指でつまんだ量)、薄すぎるのでは、と思える程度でよいです。その上に、現代流に和紙は使用せず、代用としてキッチンペーパーを敷きます。三枚におろした魚の身を載せ、ペーパーで包みこむようにかぶせ、再び薄く塩をふりかけたらラップで覆い、冷蔵保管します。塩は白身では少なく、青魚は多めに。季節で変化する脂の含有度合にあわせて、塩の量とペーパーをあてて保管する時間を長短します。
ムラなく余分な水分を抜き、身の弾力を増し、時間経過から起こる匂いまでペーパーの方に移します
直接ふり塩をすると均等に塩を付着させるのは難しいですが、ペーパー越しにしたことでムラなく余分な水分を抜き、身の弾力を増し、時間経過から起こる匂いまでペーパーの方に移しますので、魚の身は本来の味わいを落としません。まずは薄い塩から試し、魚種と自分の口、好みに合わせた分量を見つけてください。
数日も置くと塩味がつきますので、本来の刺身とは変わってしまいますが、意外やこの紙塩刺身は味わいが凝縮されていて好まれます。また、紙塩をしてから焼くと、均等に薄く塩味がついていることから綺麗に焼けますし、健康的。煮付けにも使えます。
魚の保管に苦労したであろう先人の知恵を活かした技法です。しっかり受け継いで、美味しく魚食文化を継承してみませんか。
紙塩の手順

バットなどに薄く塩をふる(塩は薄めから始めてください)

塩、キッチンペーパー、三枚おろしの身の順に置く(写真はアジ)

身の上にペーパーを置き、薄く塩をふる。ペーパーを押さえつけると少し水気を吸い、塩の量が見えて判断しやすい

バットの上、ペーパーの上に漏れた塩の量(写真はイワシ)

ラップをして冷蔵保管する

時間経過後。ペーパーが余分な水分を吸っている(塩粒は見えない)
調理例

紙塩1週間後の刺身です。美味しくいただきました。

水分多め、やわらかく鮮度落ちが早い魚にこそ有用


スーパー等で購入した魚にこそのひと仕事
紙塩焼き

焼き魚の場合、紙塩工程の塩は多めとし、焼く時の振り塩はお好みで

塩分を気にされる方は振り塩ではなく紙塩のみに
この記事は、会員制マリンクラブ(レンタルボート)Sea-Style会員様向けの会報誌に連載された内容を紹介するものです。